3月3日のひな祭りは女の子の健やかな成長を祈る大切な行事です。
チラシ寿司やはまぐりのお吸い物など、縁起の良い食べ物を用意してお祝いするのが一般的ですね。
今回は、ひな祭りの代表的な食べ物7つと夫々に込められた意味や由来をご紹介します。
特にチラシ寿司は縁起がとても良い食べ物なので、ぜひお子様と一緒に作りながら楽しいひな祭りのひと時を過ごしてくださいね。
イマドキ雛人形はコンパクトがいい!おしゃれでモダンな木製品5つを紹介
ひな祭り食べ物7つの由来(意味)

ひな祭りは旧暦の3月3日の頃(現在の3月下旬〜4月)に桃の花が咲くのに由来して、「桃の節句」とも呼ばれています。
ひな祭りに食べるものには、桃の花にまつわるものや春の訪れを表現したものが多いのが特徴です。
ひな祭りの食べ物で代表的なものには・・・
- チラシ寿司
- ひし餅
- ひなあられ
- はまぐりのお吸い物
- 手まり寿司
- 白酒
- 桜餅
などがあります。
それぞれに、我が子の健康と幸せを願う意味が込められています。
どんな意味があるのか、食べられるようになった由来と併せてひとつひとつ説明しますね。
イマドキ雛人形はコンパクトがいい!おしゃれでモダンな木製品5つを紹介
チラシ寿司

チラシ寿司がひな祭りに食べられるようになった由来は明確にはわかっていませんが、いくつかの説があります。
一番有力とされているのは、「ひな祭りには元々なれ寿司を食べていた」という説。
「なれ寿司」は平安時代、お祝いをする際に食べられていたもので、魚の中にお米を入れて発酵させたお寿司です。
現在はサバなどで作られるものが有名ですが、平安時代にはアユやフナで作られたなれ寿司がお祝い事の時に食べられていたとされています。
江戸時代になると、なれ寿司の代わりに「ばら寿司」を食べるようになりました。
ばら寿司はチラシ寿司の原型と言われています。
チラシ寿司は酢飯の上に具材をのせるのに対して、ばら寿司は酢飯の中に具材を混ぜこむものです。
なれ寿司は独特の臭さと味で好みが大きく分かれるうえ、見た目も地味。
そのため、女の子の行事には色とりどりの具材が入ったほうが良いとして、ばら寿司を食べる習慣に変わっていったと言われています。
その後、さらに華やかなチラシ寿司がひな祭りの定番の食べ物になっています。
色とりどりの具材がたくさん入っているのには、「一生食べるものに困らないように」という親の願いも込められています。
また、チラシ寿司には海老・レンコン・豆の3つの縁起物を入れるのが特徴で、それぞれにも意味が込められています。
- 海老 「海老のように腰が曲がるまで長生きするように」という長寿の願い(※海老は熱を通すと赤色になるので、さらに縁起が良いと言われています。
- レンコン 「将来の見通しがよくなるように」という願い
- 豆 「健康でマメに働けて仕事がうまくいくように」という願い
どれも子どもの長生きや勤勉さを願う縁起物です。
ひな祭りで振る舞うチラシ寿司にはぜひ入れておきたい食材ですね。
チラシ寿司はお子様と一緒に作ったり盛り付けを手伝ってもらったりと、親子で楽しいお料理時間も楽しめますね。
たくさんの願いが込められていることを知ったら、きっとお子様も嬉しい気持ちになりますよ。
イマドキ雛人形はコンパクトがいい!おしゃれでモダンな木製品5つを紹介
ひし餅

ひし餅の起源は、ひな祭りの由来でもある古代中国の行事「上巳節(じょうしせつ)」です。
元々、女の子のお祭りの日であった上巳節。
中国ではこの日に厄除けを願って母子草を入れた緑色の草餅を食べるのが習わしでした。
日本には平安時代にこの草餅が伝わり、ヨモギで作られるようになります。
江戸時代には菱の実が入った白色のお餅が、明治時代にはクチナシの実が入った桃色のお餅が加わり、現在の3色の形になっています。
特徴的なひし形は心臓の形を模していて、「子どもの健康と健やかな成長」という願いも込められているんですよ。
3色のひし餅にはそれぞれの色に意味が込められています。
- 緑:「健康」「魔除け」
- 白:「子孫繁栄」「健康」「厄除け」
- 桃:「魔除け」「先祖を尊ぶ」
また、ひし餅の色は、雪の下から芽が出てきて、やがて桃の花が咲く姿を表しています。
春の訪れを喜ぶとともに、女の子が健やかに長生きできるようにとの願いも込められているんですね。
お供えした後は、トースターなどで加熱すれば、簡単に美味しくいただくことができますよ♪
ひなあられ

ひなあられは「雛の国見せ(ひなのくにみせ)」という江戸時代にあった慣習が始まりです。
「雛の国見せ」というのは、女の子たちの雛人形遊びのひとつ。
天気の良い日にお菓子を持って、雛人形を外に持ち出し、野山や海を見せてあげるという遊びです。
この時に持って行ったお菓子が、菱餅を小さく切って持ち歩きやすくしたもので、それがひなあられの始まりです
菱餅を砕いたものなので、一般的にはひなあられも菱餅と同じように3色になっています。
ちなみに、ひなあられは関東と関西で違うんですよ。
関東のひなあられは米粒状で砂糖を使い甘く味付けされています。
いわゆる「ポン菓子」と呼ばれているものです。
一方、関西のひなあられは直径1cmほどの丸い形状で、素焼きや塩味、醤油味などバラエティに富んだ味付けが特徴です。
(画像のひなあられは関西のものになります)
イマドキ雛人形はコンパクトがいい!おしゃれでモダンな木製品5つを紹介
はまぐりのお吸い物

はまぐりが縁起物となった由来は、平安時代に貴族の間で広まった「貝合わせ」という遊びです。
「貝合わせ」は、多数並べた貝の中から一対の貝を見つけるというもの。
この遊びからもわかるように、二枚貝のはまぐりは、対の貝殻以外はぴったりと合いません。
そのため、はまぐりのお吸い物には「一生涯連れ添えるような、素敵な人とめぐりあえますように」という意味が込められています。
また、はまぐりの旬は2~4月でちょうどひな祭りと同じ時期になります。
縁起の良いものを、美味しい旬の時に食べられるのは嬉しいですね。
手まり寿司

手まり寿司とは、舞妓さんが食べる時に口紅がつかないように一口サイズにした上品なお寿司で、京寿司とも呼ばれます。
昔からひな祭りに食べられていたものではありません。
しかし、子供でも食べやすいサイズなのと、見た目の華やかさで、近年ではひな祭りで食べられることが多くなってきています。
主役の子どもたちが食べやすい大きさというのがいいですね♪
ラップに包んでてまり寿司を一緒に作るのも、おにぎり感覚で楽しそうです。
イマドキ雛人形はコンパクトがいい!おしゃれでモダンな木製品5つを紹介
白酒・甘酒

白酒の由来は、平安時代に桃の節句で飲まれていた「桃花酒(とうかしゅ)」とされています。
桃花酒は、清酒に桃の花びらを浮かべたお酒で、縁起の良いものとして愛されていました。
その後、江戸時代に桃花酒の代わりに白酒が登場し、ひな祭りで白酒を飲むのが習慣となったんですね。
本来の白酒はアルコール度数が7~12度もあるため、子どもは飲めません。
そこで作られたのが、甘酒です。
甘酒には、酒粕から作られたアルコール度数が1%未満のものと、米麹から作られたノンアルコールのものと2種類あります。
ノンアルコールの甘酒なら、1歳頃の離乳食後期からも飲めるくらいなので安心して飲むことができますよ。
白酒には、「不老長寿」や「厄除け」の意味があります。

桜餅

桜餅もひな祭りのものという印象がありますが、元々は時期を問わず食べられていました。
桃色の桜餅はひな祭りのイメージに合うこと、5月5日に食べる柏餅と対になる食べ物であること。
またひし餅よりも子供が食べやすいことから最近ではひな祭りに桜餅が売られることが多くなっています。
イマドキ雛人形はコンパクトがいい!おしゃれでモダンな木製品5つを紹介
ひな祭りの由来と意味
3月3日のひな祭りは女の子の健やかな成長を願うという意味が込められたお祭りです。
ひな祭りの由来は諸説ありますが、有力な説は・・・
元々、人形に災いを移す祓いの行事でした。
ひな祭りには「雛人形は子どもの身代わりになって、子どもに災いが降りかかることがないように」という願いが込められています。
イマドキ雛人形はコンパクトがいい!おしゃれでモダンな木製品5つを紹介
まとめ
以上、ひな祭りの食べ物と由来(意味)についてお伝えしました。
- ひな祭りの食べ物は、平安時代が起源のものが多い。
- ひな祭りの食べ物は、どれも女の子の健やかな成長を願うもの。
これまでひな祭りの時に何気なく食べてきたものには、女の子の健やかな成長への願いが込められていることがわかりましたね。
ぜひお子さんにも、ひな祭りに食べられるようになった由来や込められた意味を教えてあげてください。
誕生日とはまた違った、自分の将来に良いことがあるように願って行われる行事に嬉しさを感じることでしょう。
そしてお子さんが少し大きくなったら、一緒にお料理もしてみてください。
特に簡単に作ることができるチラシ寿司はおススメですよ。
親子で楽しい時間を過ごせるといいですね。
イマドキ雛人形はコンパクトがいい!おしゃれでモダンな木製品5つを紹介





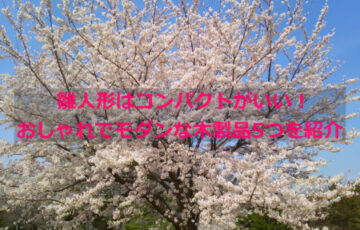


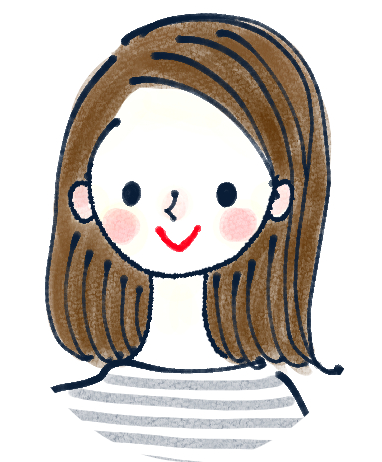 ニュースの「ちょっと気になる!」を独自目線で調査します。
ニュースの「ちょっと気になる!」を独自目線で調査します。